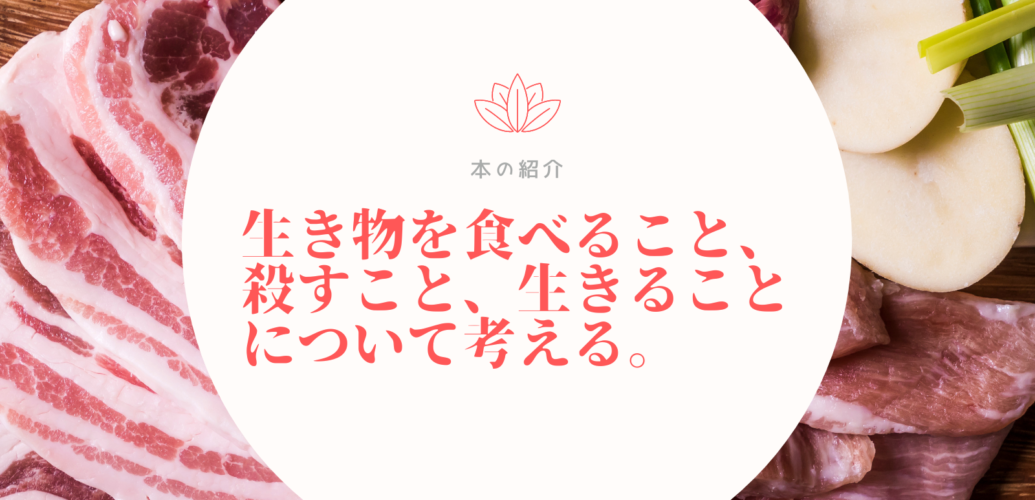赤坂憲雄氏の『性食考』(岩波書店) という本がある。
2017年に出た本だ。県随一の大型書店の民俗学コーナーを歩いていたら、平積みになっていて表紙が見えたのだ。その時点でタイトルは知っていたはずだが、どうして興味を持ったかは忘れた。しかし、少なくとも興味は持っていたので『はじめに』を読んだ。
食べちゃいたいほど、可愛い。そんな、あられもない愛の言葉を囁いたことは、残念ながら、ない(と思う)。(中略)食べることと、愛することや交わることとのあいだには、どうやら不可思議な繋がりや関係が埋もれているらしい。
そんな書き出しが、勢いよくわたしの心を鷲掴みにした。それで、とりあえず購入するに至った。
『はじめに』や目次を読めば分かるように、異なる種と交わり、殺して食べることから、神話や民話、童話においてそれがどのように扱われているかに至るまで分析が行われている。大変興味深い内容だが、結論づけることが無かったのが特徴的だった。
しかし、それがわたしにさらなる興味を齎した。他者を殺して、食べて、交わる。それらに対する興味の種が蒔かれたのだ。
これは、その興味に導かれながら読んだ書籍たちの紹介だ。
様々な肉食のあり方。
田中康弘『ニッポンの肉食』ちくまプリマー新書
この本はタイトル通り、日本の肉食文化を紹介した内容だ。
明治時代にすき焼きが広まる以前にも日本に肉食文化があったことを指摘し、それが差別を生んだことを紹介するに始まる。
日本古来の神は肉食を禁じてはいません。しかし当時の新興宗教だった仏教は殺生を禁じています。(中略)結局、貴族も僧侶も、そして庶民も楽な方を選択しました。つまり仏教の戒律は知らないふりをして肉を食べる行為を優先したのです。
そこで考えられたのが専門職を特殊な存在にすることだったと思われます。
また、動物の肉が処理される過程についても事細かに書かれている。
狩猟で得られるジビエの代表格、シカやイノシシを仕留める場面は勿論、文明の力で合理化され管理され、人間と動物共に負担を軽くされた食肉処理工場まで、生き物の命とどう向き合っているかが誤魔化さずに説明されている。
また著者の方はカメラマンなだけあって、本文中に多くの写真が使われているのが特徴だ。
肉食によってどのような文化が日本に齎されたかが分かる本である。
内澤旬子『世界屠畜紀行』角川文庫
世界各国の屠畜事情、どのような動物をどのような事情でつぶして食肉に仕立てるか、屠畜に関わる職業とそれらへの差別はどうなっているのか、などに取材した内容。
著者がモンゴルのゲルに滞在していた時、夕食の準備をしている女性たちの様子を目撃したことから『まえがき』が始まる。彼女たちが数人がかりで羊の内臓を洗っているのを見て、著者は衝撃を受ける。
すごい! これをこれから食べるんだ。そうだよな。肉って血が滴るものなんだよな。
その衝撃を起点にして、著者は行動を開始する。
どうやって肉を捌いているのか? 肉を捌くことに対して忌まわしいとか穢らわしいなどの暗い感情を抱くことは、日本以外の地域にはあるのか?
この本からは、著者のそれらの疑問への真摯な姿勢と、屠畜という職業への愛が伝わってくる。
世界では肉食文化がどのように扱われているかが分かる本だ。
異なる種と交わるために、考える。
ジーナ・レイ・ラ・サーヴァ『野生のごちそう』亜紀書房
- 棚橋志行:訳
この本はハーブから野鳥、魚介類、ヘラジカに至るまでの天然の食材を求めて採集し、狩猟して食べることにより、人類が何を得て何を失ったのかをテーマに書かれた。
新鮮なハーブを収穫するために墓地に行き、森を駆けるシカやバイソンを見て国の歴史を振り返る。食欲を満たすためにアオウミガメを獲って食べ、先住民族と土地の取引をし、平等のために野鳥を狩る女性たちを思う。わたしはこの本で描かれる、食材にされたものたちと、それに対して人類が働いた行いを読んで、人類の虚しさを思った。
わたしは、美食とは娯楽に繋がると思うし、娯楽のために生き物の命は奪われるべきではないと考えている。この本で描かれた数々のハンティングを思うと、一時の愉悦のために大量の命が奪われ、消化もされきれずに死なせることへの意味を問わざるを得ない。
食べることで私たちは、無意識のうちに自然との密接な関係を維持している。
そう本書でも指摘されている。
この本はそんな自然との関係を見直し、修復するために考えるべきことが豊富に紹介されていると思う。
繁延あづさ『山と獣と肉と皮』亜紀書房
これはひょんなことから山での狩猟に関わることになった著者が、それを取材し、猟で得られた肉を料理し、食肉と現代人との関わりについて考えた本である。
元来、出産に関わる撮影や原稿執筆を行っていた主婦としての著者の視点が、今作では大いに生かされているのが特徴だ。自らは猟の同行者ではあるが、シカやイノシシを獲って捌く現場に携わり、獲物の一部を貰い受けてから〝どうやったら「絶対、おいしく食べ」られるか〟を考え、それを実践し、完遂するまでの一部始終に絶えることなく関わっているので、このノンフィクションを自分のことのように感じられる。
また、食肉のいち消費者としてスーパーに並ぶ畜産肉に考えが及んでいるのも特筆すべき点だろう。
野生肉を食べていると話すと、「抗生剤が投与されていない肉だから安心ですね」などと言われることがある。(中略)
こういうと聞こえがいいけれど、逆にいえば、どんな病原体を持っているかもわからないし、そもそもどこで何をして、どんなものを食べて生きてきたのかわからない素性不明の獣の肉なのだ。朝のラジオで〝培養肉〟についてのニュースが流れてきた。(中略)
私たちが希求する食べ物は、生き物である必要はないのだろうか。
この本は、山で得られたシシ肉は勿論、里で育てられた畜産肉という生命と向き合い、その生命をどう繋いでいくかを考える示唆を与えてくれると思う。
東千茅『人類堆肥化計画』創元社
この本は『異なる種と交わる』という点においては、実践的な面が強い。農耕者である著者が、どうして里山に移住し、多くの生き物たちと交わり、それらを振り返って、いよいよ生きながら堆肥となろうとしているのか、その方法はいかなるものかを紹介している。
この本でわたしは、多くの生き物たちとの友愛を語ったり、かと思えば、加虐の悦びを語ったりもする。(中略)両者はつながっており分離しがたいものであるし、またこの二つだけではない。
上記の「友愛」と「加虐」は、本稿で散々触れられてきた要素だと思う。
全ての生き物は愛されるべきだし、今までも、これからも、手に手を取って助け合って行かねばならない。しかしそのためには生命の遣り取りをしなくてはならない。肉を得るために相手の生命を絶つのは、その主たる例だろう。
一見対立関係にあるようだが、引用したようにグラデーションのように繋がっていて、分離しがたいものだ。わたしたちはそうやって『異なる種と交わっている』。
著者はそれを里山で多くの生き物と対等な関係を結び、共に堆肥を作り、またそれとなることで実践しているのだ。
結局、どうして殺して食べるのか。
その意味を分かりやすく教えてくれる絵本がある。佼成出版社から出版されている、谷川俊太郎氏の『しんでくれた』という本だ。
人間は他の生き物を殺して食べなければ生きていけない。数々の家畜や魚介類、野菜や果実などの植物に至るまで、採って食べて自分の糧にしなくては生きていけない。
それらの命を無駄にしないために、我々は一生懸命に生きなくてはならない。そのための「ありがとう」であり、「いただきます」なのだ。